 天然物質-植物成分
天然物質-植物成分 コラーゲン、されどコラーゲンは緑茶が担ってくれる
【若さは追いかけるものではなく、守るもの。緑茶はその役目を担ってくれる】 私が以前、美容部員として、たくさんの女性のお肌を見てきた中で、いつも感じていたことがあります。 70代、80代でも「とてもその年齢には見えない方」が、確かにいらっしゃる。 その違いは何かというと、実は、シミ...
 天然物質-植物成分
天然物質-植物成分  栄養-栄養素
栄養-栄養素 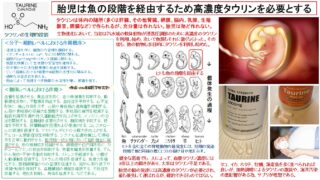 脳-能力
脳-能力  がん総論シリーズ
がん総論シリーズ  抗老化-アンチエイジング
抗老化-アンチエイジング 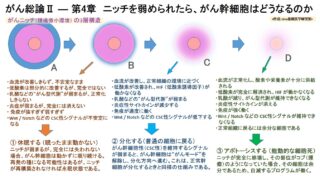 がん総論シリーズ
がん総論シリーズ 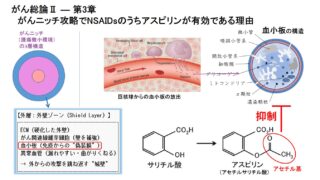 がん総論シリーズ
がん総論シリーズ 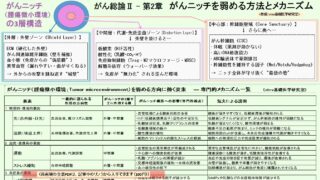 がん総論シリーズ
がん総論シリーズ  五感
五感 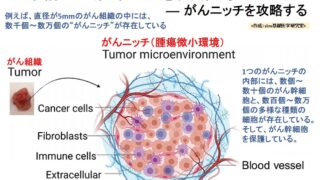 がん総論シリーズ
がん総論シリーズ 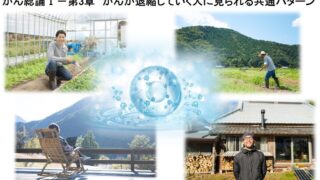 がん総論シリーズ
がん総論シリーズ 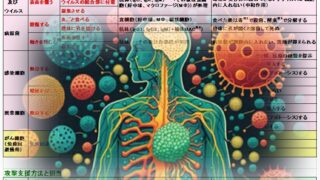 免疫
免疫  がん総論シリーズ
がん総論シリーズ  抗老化-アンチエイジング
抗老化-アンチエイジング 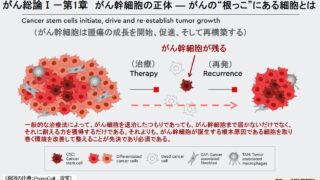 がん総論シリーズ
がん総論シリーズ  がん総論シリーズ
がん総論シリーズ 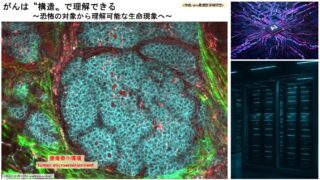 がん総論シリーズ
がん総論シリーズ